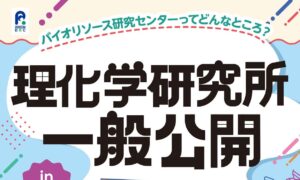物価高の波に揺れるラボ
2025年9月28日の日経新聞の朝刊サイエンス面に興味深い記事が掲載されていましたので紹介します。著者は日経新聞社編集委員の加藤宏志氏です。
記事では、現在の日本の研究現場が直面している深刻な経済的課題、特に物価高と人件費の上昇が研究活動に与える影響について述べています。物価の上昇により、研究費が実質的に減少し、研究者たちは「研究活動の維持が難しくなった」「研究の規模が小さくなった」といった声が上がっています。特に、基礎研究の衰退に対する懸念が広がっています。
加藤氏は、この問題が単なる一時的な課題ではなく、構造的な問題であることを強調しています。物価高に加えて、人件費の高騰も日本の研究環境に大きな影響を与えています。具体的には、東京都の最低賃金が2015年の907円から2025年の1,226円へと10年間で約35.2%増加したことにより、研究機関や大学では研究者や補助員の給与が増加しましたが、その結果、限られた予算での研究活動の維持が難しくなっています。また、内閣府や経済産業省のデータによれば、日本の消費者物価指数(CPI)は2015年の100から2025年には約120に達すると予測されており、これにより研究機器や消耗品の調達費用が増加し、物価高が研究費を圧迫しています。物価高と人件費の上昇は、研究活動に必要な資材や人員のコストを増大させ、実質的な研究費の削減を引き起こしています。
加藤氏は、この問題を単なる予算の問題として扱うべきではなく、もっと根本的な問題として捉えるべきだと警鐘を鳴らしています。日本の研究費は世界第3位で、2023年には約20兆円に達しています。しかし、米国や中国との格差は依然として大きく、投資額の増加だけでは解決しない問題があると指摘しています。実際に重要なのは、投資の質です。日本が投じた研究費が現場で効果的に活用されているのか、また、その配分方法に問題はないのかを検証する必要があるとしています。
さらに、加藤氏は、政府資金に頼るだけではなく、民間資金を引き寄せる方法を模索することが今後必要だと述べています。研究費の柔軟な運用方法を探ることが、今後の日本の科学技術立国としての未来を切り開く鍵となるはずです。
加藤氏の論点は、物価高と人件費上昇が日本の研究現場に与える影響を的確に捉え、これらの課題にどう対処すべきかを問いかけています。物価高や人件費の上昇が日本の科学技術に及ぼす影響は深刻であり、今後の研究投資のあり方についての再考を促しています。研究環境の改革が必要であり、効率的で質の高い投資のあり方を模索することが、日本が再び世界に誇れる科学技術立国として成長するための鍵となるでしょう。
2025年9月28日 日経新聞 朝刊サイエンス面
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO91582530X20C25A9TYC000/?fbclid=IwY2xjawNGy_BleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFzYzVhN3g2S002WlpXbnFNAR6hx8wpSJh_iIXzmQ9KpUumYVPapD7tkE1bvw-819Lj3xOvScfvSWAUwepVxQ_aem_K8Fodb6mwfdb8l7WrjZyGQ
Facebookにも投稿しています。