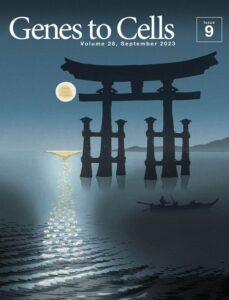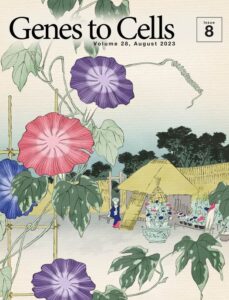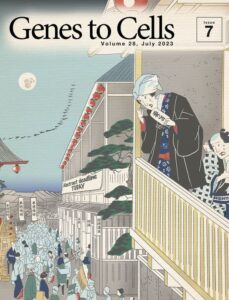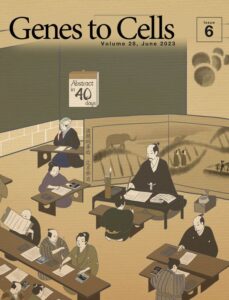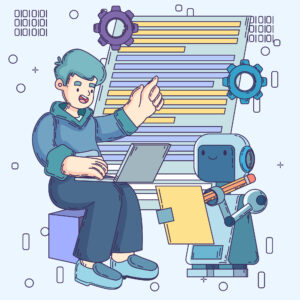寄生虫がアリに「パイルダー・オン!」
デンマーク・コペンハーゲン大学の研究チームが、寄生虫「槍形吸虫」が脳に寄生されたアリがどのような行動をするかを明らかにしたそうです。 牛などの草食動物の食事時にあたる気温が低い夜明けや夕暮れに、草の上部に移動させているそ […]
絶滅危機のオウム、ほぼ全ての個体でゲノム解読
2023年9月24日の日経新聞朝刊サイエンス面の左下に小さな記事が掲載されていました。 ニュージーランドに生息する絶滅危惧種「カカポ」で現在生息するほぼ全ての個体のゲノムをオタゴ大学などが解読したそうです。 カカポは同国 […]
わたしが毎晩、酔いつぶれるのは当たり前?
昨年(2022年)のノーベル生理学・医学賞の授賞テーマの「古代ゲノム学」が代表するように、現代人の体質や病気のなりやすさを探る「進化医学」が脚光を浴びているそうです。骨や歯に残る「古代DNA」の分析技術の進歩とデータ解析 […]
うるう秒がなくなるかも
干支が一回りする2035年までに、午前8時59分58秒のあと、午前9時00分00秒になる「負のうるう秒」が実施される可能性があるそうです。 でもこれが、コンピューターには大問題だそうです。暦が2000年になる瞬間にコンピ […]
日本分子生物学会のGenes to Cellsの9月号が発行されました。
日本分子生物学会 Genes to Cells 9月号のカバーアートです。 カバーアートのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。 https://www.mbsj.jp/gtc/cover_gallery.html […]
日本分子生物学会のGenes to Cellsの8月号が発行されました。
日本分子生物学会 Genes to Cells 8月号のカバーアートです。 カバーアートのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。 https://www.mbsj.jp/gtc/cover_gallery.html […]
日本分子生物学会のGenes to Cellsの7月号が発行されました。
日本分子生物学会 Genes to Cells 7月号のカバーアートです。 カバーアートのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。 https://www.mbsj.jp/gtc/cover_gallery.html […]
日本分子生物学会のGenes to Cellsの6月号が発行されました。
日本分子生物学会 Genes to Cells 6月号のカバーアートです。 カバーアートのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。 https://www.mbsj.jp/gtc/cover_gallery.html […]
日本分子生物学会のGenes to Cellsの5月号が発行されました。
日本分子生物学会 Genes to Cells 月号のカバーアートです。 カバーアートのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。 https://www.mbsj.jp/gtc/cover_gallery.html […]
ロボットは友達。その時、私たちはどうする?
2003年4月7日に生まれた「アトム」が20歳になり、あと90年ほどで「ドラえもん」が誕生(2112年9月3日生れ)する2023年。 日経新聞のサイエンス面で「ロボット百景」という連載が3月より続いています。 ミクロな世 […]