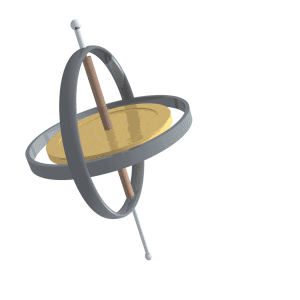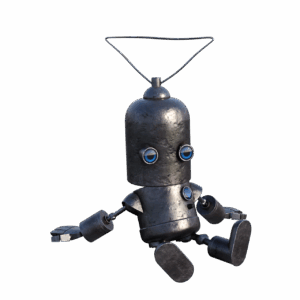やはり、生物は賢い!
鳥類なのに飛べなく、代わりに海に潜り魚を捕る、動物園の人気者、ペンギンはやはり賢かった。 ペンギンの体表面は密集した羽毛に隙間なく覆われています。従来は保温などのためと考えられていました。東京工業大学と山階鳥類研究所の研 […]
うるう年は生活に影響を、うるう秒はコンピューターに影響を与えるそうです
2017年に8時59分60秒が挿入されたように、過去27回うるう秒が使われました。これは標準時と地球の自転速度がほんの少しずれるためだそうで、最近その「うるう秒」について廃止論が議論されているそうです。「負のうるう秒」 […]
日本分子生物学会のGenes to Cellsの8月号が発行されました。
日本分子生物学会 Genes to Cells8月号のカバーアートです。 カバーアートのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。 https://www.mbsj.jp/gtc/cover_gallery.html […]
科学技術の進化で次元が増える
大きな数や小さな数で、単位と合わせて桁を表す接頭語が使われています。わが国のスーパーコンピューター「京」や「富嶽」では「ペタ」や「エクサ」。生命科学で「マイクロ」、「ナノ」。さらに光工学では「アト」という語をよく耳にしま […]
大阪万博に「メタの先」コモングランド登場!?
ヒトとロボット、現実空間と仮想空間が融合する社会「コモングラウンド(共通基盤)」が現実性を帯びてきていると、日経新聞(8月7日朝刊サイエンス面)に掲載されています。 メタバースの先にある現実と仮想を融合した世界では、カメ […]
基礎研究を好んだ「日本の物理学の父」の苦悩
日経新聞7月31日朝刊サイエンス面に「日本の原爆、新発見の手紙 苦悩の変遷」と題する記事が掲載されていました。 理系の基礎研究にはどうしてもお金が必要になります。実験に機器が必要となればその額は大きな額になります。その費 […]
隔離しかない。ワクチンを早く。バナナにも
日経新聞7月24日朝刊サイエンス面の記事です。 バナナを枯らす病原菌が世界的に猛威を振るっており、「近い将来にバナナ全滅し食べられなくなる」かもしれないそうです。 この病原菌はカビの一種の「フザリウム(Fusarium) […]
カメは歳をとらないかもしれない・・・だそうです。
南デンマーク大学と、1,200を超える世界中の動物園・水族館がかかわる「Species360」によると、生活環境が整うリクガメなど52種の75%で、老化が極めて緩やかか、無視できる状態であったそうです。 私たちのヒトをは […]
日本分子生物学会のGenes to Cellsの7月号が発行されました。
日本分子生物学会 Genes to Cells 7月号のカバーアートです。 カバーアートのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。 https://www.mbsj.jp/gtc/cover_gallery.html […]
日本分子生物学会のGenes to Cellsの6月号が発行されました。
日本分子生物学会 Genes to Cells 6月号のカバーアートです。 カバーアートのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。 https://www.mbsj.jp/gtc/cover_gallery.html […]