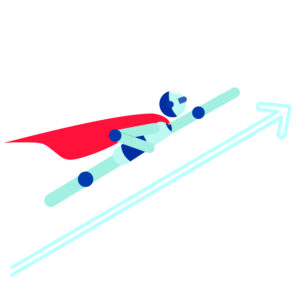今年注目の科学テーマ――AIが変える知の探究新着!!
2026年1月11日の日経新聞の朝刊サイエンス面に興味深い記事が掲載されていましたので紹介します。近年の研究動向を踏まえ、これからの科学を方向づけそうなテーマを三つに整理した内容で、なかでも強く印象に残ったのが、AIによ […]
科学技術の未来、市民が担う予見の力
2025年12月28日の日経新聞の朝刊サイエンス面に興味深い記事が掲載されていましたので紹介します。 この記事は、未来の科学技術の予測に関する取り組みと、その中で市民が果たす役割について取り上げています。特に注目されてい […]
日本分子生物学会のGenes to Cellsの2025年6号が発行されました。
日本分子生物学会 Genes to Cells 2025年6号のカバーアートです。 カバーアートのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。https://www.mbsj.jp/gtc/cover_gallery.h […]
脳科学で迫る幸せの秘訣――不安と幸福のあいだ
2025年12月21日の日経新聞の朝刊サイエンス面に興味深い記事が掲載されていましたので紹介します。日経新聞による、脳科学の視点から「幸福とは何か」に迫る内容です。 この記事が示唆しているのは、幸福感の個人差に、脳の構造 […]
第48回日本分子生物学会、開店です。
開店です。ちょっと模様替え😄 Genes to Cellsカバーのポストカード、クリアファイルは2024年版が新登場。 限定ショップもオープンしています!学会場と同じ特価で購入いただけます! https://mbsj […]
さあ、第48回日本分子生物学会、始まりました!
第48回日本分子生物学会が、12月3日(水)から12月5日(金)までパシフィコ横浜にて開催されております。 会場内ではトライスブースを出展しており、カバーアート1年分をまとめたポストカードセットや、 […]
水没する島国ツバルが示す、地球規模の適応策
2025年11月30日の日経新聞の朝刊サイエンス面に興味深い記事が掲載されていましたので紹介します。記事のタイトルは「温暖化による『水没』に直面する島国ツバルの挑戦 日本の適応戦略も転機」で、著者は久保田啓介編集委員です […]
デニソワ人—東アジアに広がる足跡
2025年11月23日の日経新聞の朝刊サイエンス面に興味深い記事が掲載されていましたので、紹介いたします。内容は「デニソワ人」という謎の古代人類に関する新たな研究成果で、特に東アジアにおけるその広がりについての発見が注目 […]